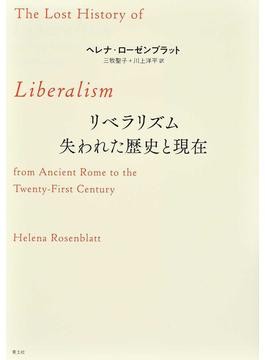
ISBN: 9784791772919
発売⽇: 2020/07/27
サイズ: 21cm/369,22p
リベラリズム 失われた歴史と現在 [著]ヘレナ・ローゼンブラット
芸術家の街モンマルトルの丘の上に屹立(きつりつ)するサクレ・クール寺院。映画「アメリ」の舞台としても知られるパリの観光名所だ。しかし、聖なる心臓(サクレクール)は、フランス革命以降、王とカトリックによる反革命のシンボルだった。「左翼の牙城(レフトウイングエリア)」に同寺院が建設されたのは、普仏戦争後にコミュニズムとフェミニズムの革命を起こした、パリ・コミューンが犯した「罪を贖(あがな)う」ためである。
それを推進したのは、王党派の将軍としてパリ民衆を血塗(ちまみ)れにした張本人、マクマオン大統領。白亜の寺院でカトリックの歓心を買い、宿敵共和派の打倒を図ったのだ。だが、結局共和派が勝利し、政教分離を革命的に断行してカトリックを切り捨てる。宗教的に中立的な公教育制度を創設したフランスは、百年かけて漸(ようや)く一つのプロジェクトを形にした。そうした歴史が凝縮されたエピソードを、随所にさりげなく挿入するセンスが、リベラリズムの失われた歴史(ロストヒストリー)を論ずる本書最大の魅力である。
そこでも予示されるように、本書は、リベラルさ(リベラリティー)をめぐる精神史をキケロから跡づけた上で、思想としてのリベラリズムの起源を、19世紀初頭のフランスに見いだす。大革命本体ではなく、歴史の暴風からその最良部分を救出しようとした、スタール夫人とバンジャマン・コンスタンが中心人物だ。アメリカ人たる著者が、リベラリズムの嫡流(ちゃくりゅう)を英米の権利論に求める通念を覆すことができたのは、彼女が近時めざましいコンスタン再評価の立役者の一人だからである。カウンター・デモクラシーを肯定的に論じたピエール・ロザンヴァロンが、先駆者として立憲君主制論者コンスタンにあえて言及したのも、この潮流の余波だろう。
他方で、そうしたリベラリズムと、民主国家・社会国家の結合可能性や、市民としての徳性(キャラクター、市民間の相互義務や公共〈コモン〉善への貢献)との結合可能性については、フランスに加えて、19世紀後半にリベラリズムを再定式化したドイツの貢献をも本書は重視している。ジョン・ロックからJ・S・ミル『自由論』への常識的なリベラリズムの思想史は、そうした仏独との交流というロスト・ヒストリーを度外視しては考えられない。アメリカがリベラリズムを掌中に収めたのは20世紀初頭であり、定着するには更に時間が必要だった。
アメリカ化された現存リベラリズムは信頼の危機にあり、非リベラルな民主主義の台頭によって脅かされているが、著者が描き出すリベラリズムは、功罪含め、自己定義の絶えざる反復にこそ本領がある。リベラルな価値の恢復(かいふく)には、失われた自らの豊穣(ほうじょう)な過去との再接合が有効であり、本書と創意工夫に富んだ訳者解説とは、そのための良き道標となるだろう。
◇
Helena Rosenblatt ニューヨーク市立大教授。歴史学、政治学、フランス学専攻。ジャンジャック・ルソーとバンジャマン・コンスタンの研究者として知られ、両者に関する単著や編著がある。












