「ヨーロッパ史」書評 終末意識に揺れるもう一つの顔
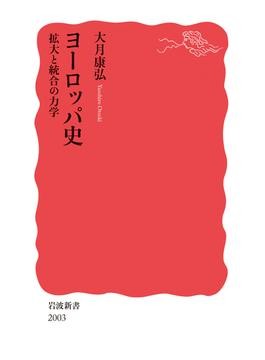
ISBN: 9784004320036
発売⽇: 2024/01/23
サイズ: 18cm/230,16p
「ヨーロッパ史」 [著]大月康弘
日本では、ヨーロッパといえば西欧のイメージが強い。5世紀の西ローマ帝国滅亡後、中世は停滞が続き、ルネサンスで古代ギリシャ・ローマ文化が復興して近代が始まったと学んだ人も多いだろう。しかし、著者はこの西欧中心の歴史観に異議を唱える。西ローマ帝国滅亡後も東地中海ではビザンツ帝国が健在であり、カール大帝などの西欧の君主もビザンツ皇帝との関係を意識し続けたからだ。
ヨーロッパを東から眺めれば、従来とは異なる歴史の原動力が見えてくる。それがキリスト教の終末意識だ。ビザンツ帝国では、神の1日は人の千年であり、天地創造から7日で世界は終わると信じられていた。当時の暦では、世界暦6千年となるのが5世紀末である。だからこそユスティニアヌス大帝は世界の滅亡を防ぐべく東西に遠征し、キリスト教を支援した。
本書はまた、ヨーロッパにおける近代社会の出現にも興味深い説明を与える。世界暦が7千年を迎える15世紀には再び終末意識が強まり、イベリア半島をイスラム教徒から奪還するレコンキスタの契機となった。この時代にイタリアがルネサンスを迎えた理由の一つは、衰亡するビザンツ帝国の聖職者たちが古代ギリシャ哲学をイタリアに伝えたことだった。その後、7千年が過ぎても世界は滅亡しなかったことで、ヨーロッパ人たちは世界の真の成り立ちに関心を抱き、自分たちの時代を「中世」と区別された「近代」「現代」として意識する。
浮かび上がるのは、合理的で普遍的なイメージとは異なる、近代ヨーロッパのもう一つの顔だ。経済学の語源であるギリシャ語のオイコノミアには「救済の摂理」という意味もあったと本書が指摘するように、その宗教性は深い。では、そのヨーロッパをモデルとしてきた近代以降の日本は、いかなる社会なのか。ヨーロッパの源流を探る本書は、同時に自らの社会を問い直すことを読者に促す。
◇
おおつき・やすひろ 一橋大教授、理事・副学長。専門はビザンツ史など。著書に『ユスティニアヌス大帝』など。












