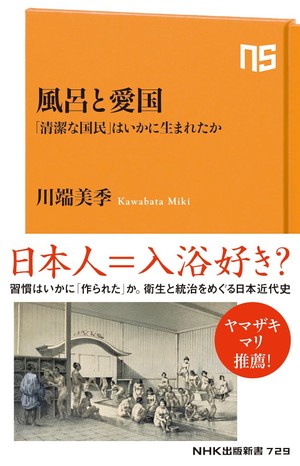
ISBN: 9784140887295
発売⽇: 2024/10/10
サイズ: 11×17.2cm/272p
「風呂と愛国」 [著]川端美季
著者によれば、「公衆浴場や入浴をめぐる歴史は非常に豊かなもの」という。確かにうなずける。
本書は江戸時代から現代までの日本人の入浴を追いかけているのだが、政治、経済、文化、公衆衛生、教育、風俗、軍事まであらゆる側面が関わっていることがわかる。
日本人は入浴が好きだ。と言っても欧米と比べて並外れてというわけではなかった。江戸時代の湯屋の分析を見ていくと、男女の混浴があったり禁止されたり、防火面での規制が強まったり、という変遷がある。
開国後、外国人の浴場観もさまざまに分かれるとの記述は興味深い。欧米では入浴を身体の清潔と結びつける時期で、日本人の素朴な入浴風景は驚きでもあったようだ。
日本人は風呂や入浴が大好き、と言われるようになったのは、明治30年代からである。この期の雑誌で、日本人は世界で最も入浴を好む、との論説が出回った。入浴の回数も多く、各地の「公浴場」は欧米より多いという。著者はこれを「東洋人種」は不潔という欧米の見方に抗するものだと分析している。風呂とナショナリズムの合体論が登場してきたわけだ。
本書の読みどころは、この延長の第六章である。明治40(1907)年、国文学者・芳賀矢一は『国民性十論』で日本の国民性のひとつに「清浄潔白」を挙げる。「日本人の様(よう)に盛(さかん)に全身浴をする国民は外にはあるまい」と入浴習慣に相当の頁(ページ)を割いている。
こういう論の、例えば「潔白」という語が井上哲次郎らの国家主義と結びついたのだろう、との分析は説得力がある。日本が東アジアを植民地化するときに公設浴場がつくられていくが、そこでは幕末の欧米人が日本人を自らの規範にもとづいた「まなざし」で見たように、今度は日本人が異なる習慣の人々をその「まなざし」で見る。そういう指摘に触れると、入浴からも帝国主義の傲岸(ごうがん)さが窺(うかが)える。視点の多面性、それが本書の魅力である。
◇
かわばた・みき 1980年生まれ。立命館大特別招聘准教授(公衆衛生史)。著書に『近代日本の公衆浴場運動』など。












