有吉佐和子「青い壺」どんな本? 2025年上半期「文庫3冠」に輝いた半世紀前の小説
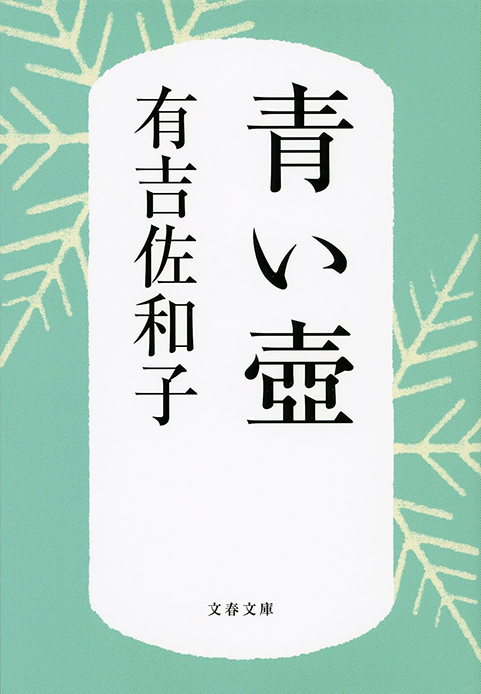
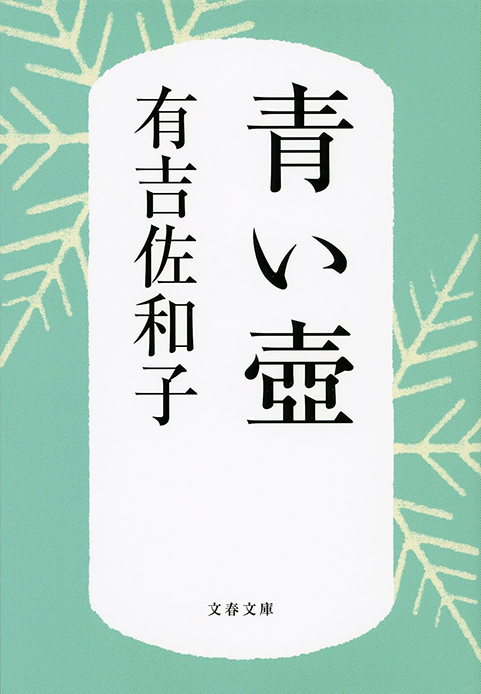
『青い壺』は昭和の人気作家・有吉佐和子(1931~1984)が1977年に刊行した、13話からなる連作短編集です。
ときは昭和の高度経済成長期。ある陶芸家が作った「青い壺」が売られ盗まれ、さまざまな人の手に渡っていきます。定年退職後の夫婦、親の介護をする娘、遺産相続に頭を痛める妻…壺が行く先々で起こる人間模様を描く、13のストーリーを収録しています。
『青い壺』は一度、絶版になっていましたが、2011年に復刊しました。
文藝春秋は復刊の経緯について「当時の文春文庫部では、出版部数を確保するため、過去の作品の発掘に目を向けていました。もともと有吉佐和子さんのファンだった編集者が資料室で『青い壺』を見つけ、読んでみてエンタメ性の高さに驚いたことが決め手となり、復刊が決まりました」と説明しています。
その後、口コミでじわじわと話題になりましたが、2023年、作家の原田ひ香さんの推薦文が入った帯のデザインに変えたことで、大きく売れ行きが伸びたといいます。同社によれば、その後の1年で10万部以上を売り上げ、累計部数が50万部を超えました。
2024年11月28日にはNHK総合テレビ「おはよう日本」で「半世紀近く前の物語がなぜ、今を生きる人たちをひきつけているのか」というテーマで『青い壺』が紹介されました。
番組では「『ああ、なんか分かるな』っていう部分が多かった」「みんないろいろ抱えて生きているんだなって思える、ちょっと前を向ける」といった、読者の感想が紹介されました。
2024年12月23日には、NHK・Eテレ「100分de名著」で、有吉佐和子特スペシャルの第4回「人生の皮肉を斜めから見つめる」として『青い壺』が登場。文庫版の帯文を書いた原田ひ香さんが、一筋縄ではいかない人生を深い味わいで描いていく有吉作品の魅力を語りました。
2025年2月には爆笑問題・太田光さんがTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」で「信じられないくらいに面白い!」と取り上げるなど、メディアでの紹介が相次ぎました。
トーハン、日販、オリコンの、いずれも2025年上半期の文庫第1位となる「文庫3冠」のベストセラーとなりました。2025年5月末時点で新装版だけで40刷56万部を発行。旧版をあわせた累計部数は80万部を突破しています。
作家の大竹昭子さんは「好書好日」に掲載された朝日新聞読書面コラム「売れてる本」で、「章を追うごとに壺は後退し、人間が前景に躍りでる大胆な設定」と、構成の巧みさを称賛しています。
時代や社会状況に目配りがなされ、会話も活き活きと弾み、コメディー映画を観(み)ているようだが、人間社会の騒々しさに比べると、壺の佇(たたず)まいはどこまでも奥ゆかしく、物静かだ。自作の映画に端役で出演する映画監督さながらに、決して前にしゃしゃり出ず、見つけてもらうのを待っているかのよう。
そして読者の目が壺に届いた瞬間、カメラのアングルはくるりと反転し、今度は私たちが壺に見つめられるのだ。この視点の転換が鮮やかで、人の価値観の移ろいやすさを実感させる。有吉佐和子「青い壺」 流転の運命、不意打ちのよう
文藝春秋で新装版の編集を担当した山口由紀子さんは、人気の理由を以下のように分析しています。
「まず、13話という構成が読みやすく、共感しやすいこと。世代も経済状況もいろいろな13の家族、家庭をのぞき見できる楽しみがあります。13話の中には必ず『知ってる』人がいます。
だから、人に薦めやすい。実際、SNSでは「母から」「読書会で」「読書仲間に」薦められて読んだ人が多いのが特徴です。一方、若い世代は、文中の女性たちの丁寧な言葉遣いなどに、昭和のレトロな香りを感じるようで、それが面白いようです。
高級レストラン・戦前の外交官の暮らし、宝石、ドレス、骨董、バラの花びらで作る枕 など、きれいで本当の豊かさを感じる贅沢なアイテムも多数登場します。文化的、教養的なものが大好きな読者が満足する一冊でもあります。
もともとは月刊「文藝春秋」に毎月連載されたもので、読者を毎月楽しませるために、有吉さんが培ってきたテーマや教養が詰め込まれ、エンタメ宝箱みたいな読みやすさがあります」

有吉佐和子は1931年、和歌山市生まれ。『華岡青洲の妻』『恍惚の人』『複合汚染』など、数々の人気作品を生み出した作家でした。
1937年1月から、父の勤務先だったインドネシアに渡り、現地の日本人学校に入学。1941年に帰国、東京、和歌山などで少女時代を送った。1949年、東京女子大英文科に入学したが、翌年病気で休学。短大英文科に転入、1952年に卒業。
大学卒業のころから同人雑誌「白痴群」に加わり、さらに、三浦朱門、曽野綾子氏などと第十五次「新思潮」に参加。1956年、「文学界」に発表した「地唄」が芥川賞候補作になり、文壇に登場。曽野綾子氏とともに才女時代の到来として注目された。1959年に、出身地和歌山の人と風土に目を向け「紀ノ川」を婦人雑誌に連載、代表作の一つとなった。1961年には「婦人公論」に「香華」を連載、婦人公論読者賞、小説新潮賞を受賞した。
以後、「華岡青洲の妻」「海暗」「恍惚の人」「和宮様御留」などの作品を精力的に発表。当時の日本社会が抱えていたさまざまな社会問題に鋭い目を向け、とくに、「恍惚の人」は老人問題を取り上げて、大きな反響を呼び、ミリオンセラーになった。また、農薬や化学物質に依存する現代の農業のあり方を問うた作品に朝日新聞連載の「複合汚染」があり、それぞれに題名が流行語となった。有吉佐和子さん急死/社会問題に鋭い視点 「恍惚の人」や「複合汚染」1984年08月30日(木)夕刊
1984年8月、53歳で死去しました。
好書好日編集部がお送りするポッドキャスト「本好きの昼休み」で、山口さんのインタビューを音声でお聴きいただけます。












