「尻尾と心臓」書評 会社員それぞれの生き方に共感
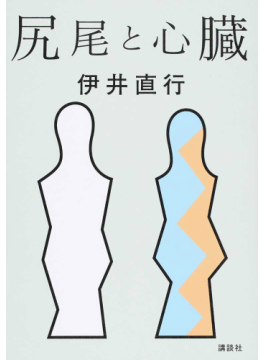
ISBN: 9784062200523
発売⽇: 2016/05/24
サイズ: 19cm/305p
尻尾と心臓 [著]伊井直行
「企業小説」とも「経済小説」とも違う「会社員小説」だ。仕事での試行錯誤を通じて変容していく会社員の内面にじっと目をこらす本書を読んでいると、「平凡なサラリーマン」ではない姿が浮かび上がる。
九州が本社の食品問屋・商社「柿谷忠実堂」の東京にある子会社「カキヤ」が小説の舞台。九州本社から出向してきた乾紀実彦、外資系経営コンサル会社から柿谷グループの別会社に転職してきた笹島彩夏が、親会社肝いりの新規事業開発でタッグを組む。GPSを利用した営業補助システム「セルアシ」の商品化が目標だ。ところが、親会社を敵視するカキヤ社内で様々な抵抗に遭い……と紹介すると、「なんだ、普通の企業小説じゃないか」と思うかもしれないが、かなり違う。苦労した末のサクセスストーリーの経過ではなく、主人公二人が仕事、会社、家族について思い悩む描写が濃厚に展開される。
乾は開発責任者のプレッシャーから、あらゆる仕事相手が自分をどう思うか常に気に病む。仕事ができる笹島も、目標達成への不安、乾への嫌悪感でストレスを抱え込む。しかし、二人はちょっとした仕事の進展で元気を取り戻す。
こうした遅々たる歩みに会社員として共感してしまう。事業開発の苦境で「一発逆転」のような派手な場面はないが、会社員のありのままを映しているのだ。
カキヤの気難しいワンマン社長、新技術導入を断固拒否する古参社員、企業小説では敵役にあたる登場人物だが、それぞれ紆余曲折(うよきょくせつ)してきた会社員の生き方が示され、存在感がある。
「平凡とか灰色とか、そういうイメージで見られがちな会社員も、実はそれぞれの人生を背負った上で働いている」
笹島がもらすこの言葉は、都会の雑踏に紛れてしまいがちな会社員がアイデンティティーを得た実感だ。当たり前のような言葉だが、本書を読むとじわっとしみる感動を覚えた。
◇
いい・なおゆき 53年生まれ。83年に群像新人文学賞。01年『濁った激流にかかる橋』で読売文学賞。












