「天使はなぜ堕落するのか―中世哲学の興亡」書評 「神の存在証明」必要だった理由
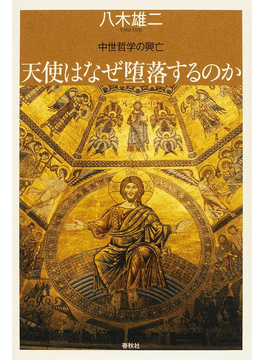
ISBN: 9784393323304
発売⽇:
サイズ: 20cm/593p
天使はなぜ堕落するのか―中世哲学の興亡 [著]八木雄二
ヨーロッパの中世哲学の一流のレベルから見れば、デカルトの『省察』は大学生の卒論程度だ、と著者は「あとがき」に書いている。私はこの大言壮語にあきれて本書を読み始めたのだが、読み終わると、確かにそういう気がしてきた。たとえば、デカルトによる神の存在証明は、アンセルムス以来の中世哲学の流れの中にあり、それを知らないと十分に理解できない。しかし、中世哲学を読んでみてもよくわからない。退屈なだけであった。実は、私は本書を読んでようやく、中世哲学がどういうものなのか納得できたのである。
本書には、私がこれまで知らなかった、そして、知りたかったことがつぎつぎと出てくる。著者は誰かの権威にもとづいて書いているのではない。わからないことをわかったふりをせずに自力で考えてきた結果として、本書がある。それを読むのは、まことにスリリングで壮快な体験である。ここで詳細を伝える余裕がないので、一例だけをあげておこう。私がつねづね疑問に思っていたのは、なぜ神の存在を証明する必要があるのか、ということである。その時代には無神論者はいなかったし、キリスト教の異端派も、イスラム教徒も同じことをやっていた。だから、「神の存在証明」を必要としたのは、誰かに対してではなく、いわば「哲学」に対してであった。
12〜13世紀のヨーロッパには、イスラム圏からアリストテレスなどギリシャの哲学が本格的に導入された。しかし、それだけではない。その時期、ヨーロッパ各地で発展した自由都市で、自治的な組合組織である、大学が創(つく)られた。それがもたらしたのは、論争によって真偽を決するという態度である。大学で支配的だったのは唯名論者であり、いわば「ソフィスト」たちであった。教会や修道院はそれを取りこみつつ、自己を防衛しなければならなかった。神学、あるいは、神の存在証明の執拗(しつよう)な議論はそこから出てきたのである。「中世」のヨーロッパに「古代」の哲学が回復されたのは、前者が古代アテネの状況と似ていたからだといえよう。
*
春秋社・5040円/やぎ・ゆうじ 52年生まれ。著書に『スコトゥスの存在理解』『イエスと親鸞』ほか。












