リディア・デイヴィス「話の終わり」書評 感情の記憶の堆積、恋情の地層
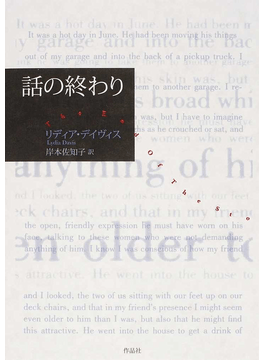
ISBN: 9784861823053
発売⽇:
サイズ: 20cm/273p
話の終わり [著]リディア・デイヴィス
なんとも不思議な恋愛譚(たん)だ。恋の甘やかさよりは退屈さやしんどさに描写の比重が置かれ、恋人が去ってからの思いや後日談が物語の大半を占めている。
著者のリディア・デイヴィスは『ほとんど記憶のない女』(白水社)でも知られる奇妙な味の短編の名手だ。緻密(ちみつ)なのにどこか滑稽で、論理的でありながら(あるがゆえに?)妄想的でもあるのが彼女の持ち味である。この初の長編でも、その作風は遺憾なく発揮されている。
主人公は大学で教える30代の女性教師。パーティーで出会った12歳年下の恋人とあっさり恋に落ち、葛藤の多い交際を経て半年あまりで彼は去る。しかし彼への思いを断念できない彼女は、その後も彼を追い回す。
アパートをつきとめ新しい恋人に嫉妬し、職場のガソリンスタンドに押しかける。ストーカーと化した彼女を、彼も強くは拒まない。この曖昧(あいまい)な関係がさらなる妄想を育んでいく。
その描写は極めて特異だ。硬質かつフラットな語り口が精密な描写を続けるほど、全体のピントがぼやけてくる。“精細度の高い曖昧”さの中から、不意に“熱く苦い紅茶”のようなリアルなイメージが立ち上がる。
さらにそこにはメタフィクショナルな構造がある。ヒロインとしての「私」と、夫の父親の介護をしながら本作を書く「私」。錯綜(さくそう)する時制と移動する視点が不思議に混乱を招かないのは、「私」の感情が「彼」の追憶に常に照準しているためだろう。
本作を読んでいて、しきりに思い出された言葉がある。「忘れようとしても思い出せない」(赤塚不二夫)。そう、過ぎ去ったエピソードを細部に至るまで記述し尽くそうとする私にとって、彼の顔こそは“忘れようにも思い出せない”対象なのだ。思うに任せない感情の記憶が堆積(たいせき)して、恋情の地層を形成していく。
本書の発表が1995年であったことも興味深い。ネット直前のあの時代、携帯メールもツイッターもフェイスブックもない時代の恋愛は、曖昧さや妄想性といった“美質”の光背を確かに負っていた。
評・斎藤環(精神科医)
*
岸本佐知子訳、作品社・1995円/Lydia Davis 47年生まれ。米国の作家。『ほとんど記憶のない女』など。












