「中世は核家族だったのか」書評 疫病や災害が夫婦の結合強めた
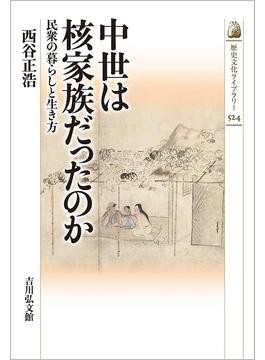
ISBN: 9784642059244
発売⽇: 2021/05/19
サイズ: 19cm/215p
「中世は核家族だったのか」 [著]西谷正浩
核家族と中世。奇妙な組み合わせに感じるのは、中世の特徴を家(いえ)制度の成立と見る通説が前提にあるからだ。平等な分割相続が、家名や家産を長男が独占する単独相続へと変わり、特に女子は排除された。この傾向は、貴族や武士の間で南北朝時代を画期に進み、戦国時代で民衆へ達する。
だがこの説明では、民衆家族の実態は、大半の時期で抜け落ちてしまう。史料の欠落を打開するため、著者は歴史人口学や気候学、集落遺跡の発掘・復原(ふくげん)等の最新の知見を、社会経済史の蓄積と融合させる。すると、成人した子供はみな生家を出て夫婦で独立した世帯を営むという「核家族規範」が浮かびあがる。
きっかけは、古代末期の疫病や自然災害の多発だった。崩壊した共同体から放り出された民衆は、夫婦間の結合を分業で強めて危機を乗り切る。鎌倉時代の有力農民である名主(みょうしゅ)層でも、非親族を含めた複数の世帯を抱えながら、住宅から食事・家計まで別々で、決して大家族ではない。名主の地位も不安定で、小百姓と身分差はなかった。
ところが中世末期、地侍(じざむらい)になった有力農民が、系譜や由緒を創って身分上昇を狙う。武家に倣って家の永続を図り、やがて世襲制の庄屋となる。ただし親子二世代同居の直系家族が、全階層で一般化するのは近世も後半。中世の家族形態は、それほど長く持続した。
本書の明快さは、家族の変貌(へんぼう)を、農業経営や村落の身分秩序の長期的な変化と結びつけ、中世社会の全体に有機的に位置づけた点にある。実家を出ながら結婚まで母親の世話になる「母懸(ははがかり)」の若い男性の存在など、犯罪や裁判の荘園文書から村の意外な慣習を引き出す史料捌(さば)きも興味深い。
生存戦略として培われた家族の形。この「中世人の貴重な体験」は、核家族の規範さえ動揺し、当時と同じく「家筋(いえすじ)」に無関心な「祖先なき者」となった私たちにとり、未来を占う想像力の幅を広げてくれる。
◇
にしたに・まさひろ 1962年生まれ。福岡大教授(日本中世史)。著書に『日本中世の所有構造』など。












