「感性文化論」書評 聴覚より視覚優位へと認識転換
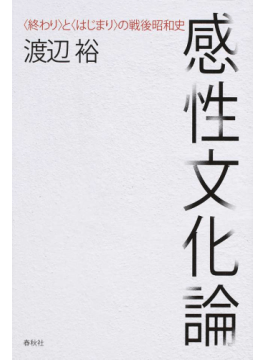
ISBN: 9784393333525
発売⽇: 2017/04/25
サイズ: 20cm/319,33p
感性文化論―〈終わり〉と〈はじまり〉の戦後昭和史 [著]渡辺裕
戦後のある時期まで、鉄道の案内の多くは聴覚を通してなされていた。車内では車掌が、駅のホームでは駅員が次の駅や乗り換えなどを肉声で放送し、客はそうした声に耳を傾けた。車掌の語りそのものが一種の職人芸と化すこともしばしばあった。だがある時期から車内やホームに電光掲示板が普及するようになり、放送は録音された短いものに変わるなど、視覚の占める比率が高まった。
本書を読むと、聴覚優位の文化は1964年の東京オリンピックの頃にはまだあったことがわかる。それをよく示すのが、開会式を中継したNHKのラジオとテレビの放送である。当時のテレビは白黒が主流で、ラジオを聴く人々の割合がいまよりも高かった。ラジオではアナウンサーが美文調のレトリカルな表現で人々を引きつけたばかりか、テレビの実況中継にすらラジオとよく似た特徴を認めることができた。
こうした聴覚優位の文化は、戦前から受け継がれたものであった。NHKラジオには、有名な合戦や野球の早慶戦をアナウンサーが実況する「架空実況放送」という番組まであったが、66年には終わっている。ラジオから白黒テレビへ、そしてカラーテレビへとメディアの主役が移り変わるなかで、聴覚優位から視覚優位へと感性文化のパラダイムが徐々に転換していったのである。
それは決して、メディアだけで起こった転換ではない。ほぼ時を同じくして、鉄道でも起こっていた転換でもあるのだ。ここに戦後史の「断層」があることを発見した本書の意義はまことに大きい。
その背景には、音楽や声をはじめとする「音」が歴史とどう関わるかを考えてきた著者ならではの視点がある。それはただ史料を読み込むだけでは到達し得ない視点と言ってよい。感性という文字化されにくい対象を掘り下げ、新たな戦後史の見方を示した著者の洞察に心から脱帽する。
◇
わたなべ・ひろし 53年生まれ。東京大教授(美学芸術学、文化資源学)。『聴衆の誕生』でサントリー学芸賞。












