「在宅無限大 訪問介護師がみた生と死」書評 日常の風景で迎える大切な最期
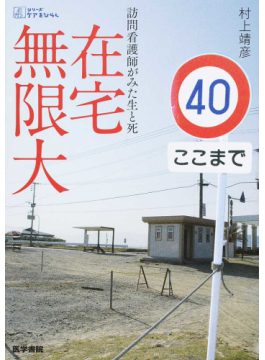
ISBN: 9784260038270
発売⽇: 2018/12/25
サイズ: 21cm/253p
在宅無限大 訪問介護師がみた生と死 [著]村上靖彦
少し前に興味深い記事を読んだ。病気の人間が死の直前に「愛してる」と言う、そんなのは実際はありえない、と病院の医師たちは考えるが、実は在宅の看取りでは普通にありえることだという。訪問看護師らにインタビューを重ねた著者もまた、病院での死が一般的になったことで「医療者も含めて、私たち全員がかつての死の姿を忘れた」のではと投げかける。
訪問看護師らが語る死は驚きに満ちている。ある看護師は「悲しみではありません」「しんみりっていうのもない」と断言する。死を軽く考えているからではない。在宅死を選んだ家族たちの「ちゃんと家で看取れてよかったー」といった達成感に満ちた言葉を受け取ってきた経験を経た言葉だ。死に行く人が、日常の風景の中にいることの大きさを思う。病院の規則や慣例に縛られることなく、家族が自然体でいてやれることで、死に行く人の願いは叶えやすくなる。結果的に家族も悔いの残らない看取りが実現する。例外は勿論あるだろうが、大量の患者を預かる病院という現場では一般に、患者も看護師も医療措置に関わる匿名の「誰か」になってしまう、という指摘には唸らされる。
本書では独居のケースも触れる。急に退院させられた中年男性は、年齢の制限で介護保険のヘルパーに頼れず、絶望して自殺した。ヘルパーが入って「温かいおみそ汁かなんかでも用意」できれば違ったのでは、という看護師の言葉は重い。自殺でこそ無かったが、昨年やはり弱りきって退院させられ、公的な助けを得られずに独身の知人が死んだ。著者は「自分自身を実現する本来的な死は、孤独においてではなく、対人関係のただなかで生じる」と書く。病気で弱った人間を守る命綱は人の?がりであり、限られた疾病以外は年齢によってヘルパー派遣の可否が決まってしまう現行制度の不備は「生涯独身」が増えゆく中、広く認識されてほしい。
◇
むらかみ・やすひこ 1970年生まれ。大阪大教授(基礎精神病理学)。『摘便とお花見』『自閉症の現象学』など。












