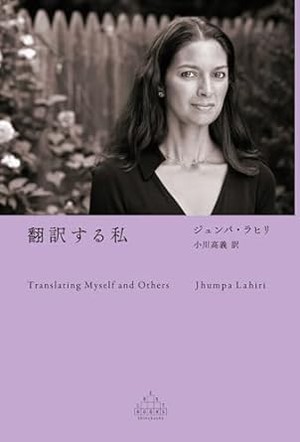
ISBN: 9784105901998
発売⽇: 2025/04/24
サイズ: 18.8×2cm/192p
「翻訳する私」 [著]ジュンパ・ラヒリ
ベンガル人の両親の元イギリスに生まれ、アメリカで育ったラヒリ。ベンガル語と英語、二つの言語の狭間(はざま)で成長した少女はやがて英語で創作を始め、一躍成功した作家となった。それから十数年後、彼女は大胆な言語的冒険に飛び込む。イタリアに居を移し、イタリア語で創作を始めたのである。本書には、自分を「物心ついてからずっと翻訳について考えて生きてきた人間」だと定義するラヒリの、翻訳をめぐり刻々と変化する思考の痕跡が収められている。
自ら選び取った外国語で書き、読むとはどういうことなのか。ラヒリはそれを、ドア、視力の喪失、接ぎ木、といったメタファーで提示する。さらにはスタルノーネの作品を翻訳し、獄中で書かれたグラムシの手紙を読み、翻訳という行為自体を様々なものに翻訳していく。オウィディウスの『変身物語』からエコーとナルキッソスの神話を引き、翻訳と創作の関係を考える「エコー礼讃(らいさん)」の章はとりわけ興味深い。時に声を繰り返すエコーとして、時に水面を覗(のぞ)き込むナルキッソスとして、多言語の森を駆け抜けていくラヒリの駿足(しゅんそく)に目が眩(くら)む。
ある言語の中に身を置き深く潜っていくことで、思考が泡立ち、波打ち、新たな陸地へと流れ込んでいく。その過程を捉えた本書は、ラヒリの小説と同様、彼女が長く大切に書き溜(た)めたメモをこっそり見せてもらっているような親密さに満ちている。序文とあとがきに綴(つづ)られる母との逸話は忘れ難い。五歳のラヒリは母の日のカードを書くにあたり、普段ベンガル語で「マー」と呼んでいる母を「ママ」という英語に翻訳すべきかためらった。それから数十年後、『変身物語』の英訳を進めるラヒリは、死を前に変容しつつある母を見守っている。やがて死者となる母を、彼女はどう訳したか。一人の人間の内に降り積もった時間と思索が見事に結晶する、こんなにも美しい翻訳を見たことはない。
◇
Jhumpa Lahiri 1967年生まれ。作家。『停電の夜に』でピュリツァー賞など。『見知らぬ場所』『べつの言葉で』など。












