「ウラニウム戦争」書評 科学者が抱え込んだ根源的苦悩
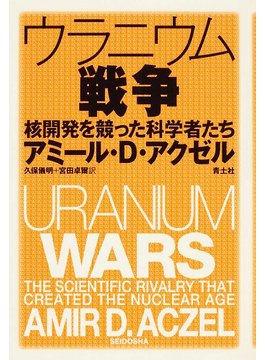
ISBN: 9784791765263
発売⽇:
サイズ: 20cm/321,21p
ウラニウム戦争―核開発を競った科学者たち [著]アミール・D・アクゼル
「誤解されると困るが」とその原子物理学者は前置きして、「広島への原爆投下を知ったとき、我々の机上の計算が現実になるとはこういうことかとの感慨をもった」とつぶやいた。戦時下の日本で原爆製造計画(ニ号研究)にかかわった科学者の正直な言を聞いたことがある。
自らの研究が人類の不幸につながるとのジレンマ、二十世紀の科学者が背負いこんだ根源的な苦悩である。
本書は一言でいえば、ウランという元素がいかにして発見され、それが原子爆弾までゆきついたのか、その過程を丹念に辿(たど)った書である。むろん読み方は多様だ。二十世紀の先端を行く科学者たちの研究史、地球上に存在する物質の謎を解きあかす科学史、科学研究と政治思想の関係史などがすぐに思い浮かぶが、私は第1次大戦(毒ガス)と第2次大戦(原爆)に共通する大量殺戮(さつりく)兵器がいかに科学者の良心を麻痺(まひ)させたか問うているとの思いで読んだ。たとえばオットー・ハーンは、毒ガスの性能を高める実験を進めたが、自伝の中で「もはやいかなる良心の咎(とが)めも感じることができなかった」と弁明したという。
そのハーンがナチスの原爆に協力した理由はどこにあるか、あるいはドイツの原爆研究の要だったハイゼンベルクをどう見るかなど、著者はその状況について客観的記述に徹している。
ウラン235は核分裂を引き起こすが、天然ウランから分離するのは容易でない。予算、人員、施設は政治の側の問題だが、それに思惑がからんだ瞬間に科学は自立か隷属かを迫られる。二十世紀は隷属であった。しかしそこにはキュリー夫妻、ベクレル、ラザフォード、ボーア、マイトナー、フェルミ、アインシュタインなど多数の科学者たちのそれぞれの状況下での闘いや煩悶(はんもん)があった。彼ら一人一人につきつけられた刃(やいば)について、著者は詳細にその生き方を整理している。
それゆえ「ウランが秘めている力をクリーンなエネルギーとして利用」が可能か、人類は今、岐路に立っているとの結論に首肯せざるをえないのだ。
*
久保儀明ほか訳、青土社・2520円/Amir D. Aczel UCLAバークリー校で数学を専攻。作家。












