「テレビ越しの東京史」書評 1964の成功から遠く離れて
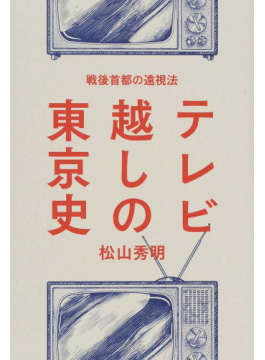
ISBN: 9784791772322
発売⽇: 2019/11/25
サイズ: 19cm/333,29p
テレビ越しの東京史 戦後首都の遠視法 [著]松山秀明
今年、メディアに問われているのは、オリンピック周辺で巻き起こる熱狂の裏で潰される声を聞き取る力だが、むしろ、熱狂を扇動するメディアが目立つ。東京は、かつてのように過度な憧れを向けられる場所ではないが、東京が盛り上がれば震災復興にも繫がる、との誤認が大手を振る。
「戦後東京の枠組みを規定した最大のメディアは、文学でも、写真でも、映画でもなく、テレビではないか」とし、ブラウン管(この言葉も間も無く朽ちる言葉だ)越しに東京を問う一冊が、その始点として繰り返し持ち出すのが一九六四年の東京オリンピック。
なにせ、「テレビによって〈東京〉での祝祭が演出され」たことで、「七五〇〇万人もの人びとが見る『テレビ・オリンピック』が成功した」のだ。それまで「テレビのなかの東京」には「都市下層」の人々も映し出されていたが、やがてテレビは「未来都市・東京」を映し出すことに躍起になる。
相次ぐ公害問題を追うなど高度経済成長の歪(ゆが)みを映したり、一部のホームドラマが「〈東京〉の喪失に抵抗した」りしたが、東京とはこういう場所であると規定するテレビは少なくなり、世界へ羽ばたいていく都市としての東京を、テレビは捉えきれなくなる。
一九九一年に放送されたトレンディドラマ「東京ラブストーリー」の赤名リカが、東京について「何があるか分かんないから元気でるんじゃない」と語るシーンが象徴的だと著者。テレビは「テレビのなかの東京」と「東京のなかのテレビ」を循環してきた、とする言葉遊びのような論旨を読み込むと、確かに戦後から現在までの東京を「遠視」してきた変遷が見えてくる。
昨今のテレビは「双方向性」なる言葉で視聴者に迎合することが多い。「テレビなんて持ってない」という声がそこかしこで聞こえる今、テレビがもう一回、オリンピックが作る熱狂にすがろうとしている。それはだいぶ滑稽に思える。
◇
まつやま・ひであき 1986年生まれ。関西大准教授。共著に『メディアが震えた』『新放送論』など。












